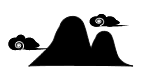×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
長らく間をあけてしまいました。
松永久秀はマイナー武将などではない、という話を載せたので、その業績をご紹介。
少し前になるが、新聞にも載っていたような話。
戦国期、館や砦に毛がはえたような小さな城から、強固な城壁を備えたいわゆる「城」と言って想像するモノの建築が一般的になっていく過程で、多用されていく建築物に、「多聞(たもん)」とか「多聞櫓(たもんやぐら)」と呼ばれるものがある。
「多聞」は城壁・城門が武器庫を兼ねているというもの。(広辞苑にも載っている。)
城壁の中が長屋状になっていたり、城門の屋根裏部分に武器庫が乗っかっているような状態だったりだから、例えば城門を抜けようとする敵を、そこに潜んでいて頭上から槍でめった突き、とかそういうこともできるわけで。
重要な守りの要になるのですわな。
大坂城の城門なんかもこの技法が取り入れられていたと記憶している。
で。
この建築技法を最初に取り入れたのが、松永久秀だというのである。
そもそもネーミングにしてからが、松永久秀の居城のひとつであった「大和多聞城」の城壁で使われていたことからきているという。
ちなみに、新聞に載っていたというのは、この「大和多聞城」があったと思われる城跡から「多聞櫓」であろう遺構が見つかったからであったと思う。
そんなわけで、松永久秀は戦国史研究をしている人たちの間では、当時の文化・技術を知るうえで、けしてはずせない武将のひとりなのだ。
松永久秀はマイナー武将などではない、という話を載せたので、その業績をご紹介。
少し前になるが、新聞にも載っていたような話。
戦国期、館や砦に毛がはえたような小さな城から、強固な城壁を備えたいわゆる「城」と言って想像するモノの建築が一般的になっていく過程で、多用されていく建築物に、「多聞(たもん)」とか「多聞櫓(たもんやぐら)」と呼ばれるものがある。
「多聞」は城壁・城門が武器庫を兼ねているというもの。(広辞苑にも載っている。)
城壁の中が長屋状になっていたり、城門の屋根裏部分に武器庫が乗っかっているような状態だったりだから、例えば城門を抜けようとする敵を、そこに潜んでいて頭上から槍でめった突き、とかそういうこともできるわけで。
重要な守りの要になるのですわな。
大坂城の城門なんかもこの技法が取り入れられていたと記憶している。
で。
この建築技法を最初に取り入れたのが、松永久秀だというのである。
そもそもネーミングにしてからが、松永久秀の居城のひとつであった「大和多聞城」の城壁で使われていたことからきているという。
ちなみに、新聞に載っていたというのは、この「大和多聞城」があったと思われる城跡から「多聞櫓」であろう遺構が見つかったからであったと思う。
そんなわけで、松永久秀は戦国史研究をしている人たちの間では、当時の文化・技術を知るうえで、けしてはずせない武将のひとりなのだ。
PR